日本の国の鳥は、キジです。
長い尾羽、派手な羽の色、そしてその堂々とした立ち振る舞いは、日本の国鳥としての威厳を表しているかのよう。
田畑で見かけることの多いキジは、大昔から日本人にとって馴染み深い野鳥であったようです。
しかし、現在では日本人の先祖が目にしたことのない「キジ」が数多く見られることは意外に知られていないかもしれません。今回はそんなキジの生態について紹介します。
 トリハカセ
トリハカセそれでは早速はじめましょう!
興味のある項目を目次から飛んでくださいね。
キジの生態:入門編
キジ | Japanese Pheasant | Phasianus versicolor |キジ目キジ科キジ属
レア度:☆☆☆☆☆☆☆☆★★(2/10:身近ですこし探すと見つかる)
見られる季節:1年中
見られる場所:北海道以外の日本全国
見られる環境:農耕地
餌:雑食(植物、爬虫類などいろいろと食べる)
キジのオスは全長80cm、メスは全長60cmと、カラスよりも大きい迫力のある鳥類です。
オスは緑や青色に光沢を放つ羽や、真っ赤な顔に特徴づけられ、他の種に見間違うことはないでしょう。
キジは様々な餌を食べる雑食性の鳥であり、トカゲや昆虫などなんでも食べます。
さらに、キジの雛は生まれてすぐに歩き始め、親鳥と共に行動をするため、餌をわたすような育雛はおこないません。

キジの特徴 – 派手なオスと地味なメス
 トリハカセ
トリハカセメスの姿は、あまり有名ではありませんよね。
オスが派手な一方、メスは一見すると地味で、全身が黄色味の強いベージュ色をしており、ところどころに黒色の斑点があります。
メスは、同じキジ科のヤマドリと酷似します。
類似するヤマドリとの重要な識別点として、やや長い尾羽の先端には、白色の点がないことが挙げられます。
また、ヤマドリのメスは全身の羽色に(黄色味ではなく)赤色味が強く、尾羽の先端が白いことが特徴で、キジのメスと見分けることができます。

キジの生息地と生態
キジは、北海道を除く日本本土の低地に分布しています。
一年を通して低地、特に田畑のまわりや河川敷といった野原で生活しています。
4月から6月の繁殖期は、オスを最も見つけやすい時期です。
なぜなら、オスは自身の縄張りを誇示し、メスを誘うために「ホロ打ち」と呼ばれる大声で鳴きながら、翼を体に打ちつける行動でアピールを行うためです。
 トリハカセ
トリハカセドドドド!と翼を打ち鳴らす姿は大迫力!
繁殖生態
生まれた子供が次の世代を残すまでの世代時間は、5年とされています。1度に産む卵の数は6–12個と子沢山です。
夏は縄張りを作って繁殖しますが、メスは複数のオスの縄張りを訪れ、さまざまなオスと子供を作るようです。
一方で冬には、オスとメスがそれぞれ別の群れを構築し生活します。
主な餌は植物の種や果実、昆虫ですが、ときにはカエルやヘビなども食べます。
カエルやヘビなどの消化できない骨をペリットとして吐き出すような生態をもつことは意外にもあまり知られていません。
ちなみに葛飾北斎は「雉と蛇」という名前で、キジがヘビを食べる様子を作品として残しています。
コウライキジ:外来種のキジが日本の自然を脅かす
日本では、ユーラシア大陸にひろく分布するコウライキジも観察することができます。
しかし、コウライキジは元来日本には生息せず、ハンティングなどを目的として放された「外来種」です。
江戸時代以降に対馬、北海道などさまざまな場所で放たれ、現在は野生化しています。
コウライキジは、現在ではヨーロッパや北アメリカにも移入され、野生化しています(IUCN分布図)。
 トリハカセ
トリハカセしかし、コウライキジは個体数が多いとは言えず、なかなか見られません!
キジとコウライキジは別種?
これまで日本のキジは、大陸に分布するコウライキジの亜種とされてきました。
しかし、2022年の遺伝子に関する研究の結果から、両種が別種であることが示されました。
2種が別種であるときに想定される遺伝子配列の違いの割合よりも、キジとコウライキジの遺伝子配列は異なっていることがわかったのです。
この発見から、日本に生息するキジは独立種であり、日本固有種であることが確かめられたのです。


コウライキジの特徴
コウライキジのオスの大きな特徴は、体下面が黄色く、首に白い帯があり、頭の側面に灰色の線があることです。
コウライキジのメスを、キジのメスと区別することはオスに比べると難しいですが、
コウライキジのメスは耳羽(ほっぺに見える箇所)の赤色味が弱いことや、全体的な体色がキジよりも黒く見えます。
オスについては識別点は明白ですが、メスの場合は体の色や顔の模様から総合的な判断が必要です。
特に幼鳥メスの場合、キジ・コウライキジともに黄色味が強くなるため、年齢も考慮する必要があり、難易度は高めです。

日本のキジも、海外では外来種
ちなみに日本のキジはハワイに放たれ、外来種となっています。
ハワイの生態系はさまざまな外来種によって乱され、現在では元来の姿はとどめておらず、外来種の宝箱のような様相に。
また、国内でもキジが元来生息しない離島に持ち込まれ、野生化している場所もあります。
こうした問題は、海外からの外来種問題と比べて焦点が当たりにくく、解決は容易でないかもしれません。

鳴き声
オスは「ケン ケン」と激しい鳴き声を出します。ときには数分おきに1時間も鳴き続けます。
メスは「ケケ ケケ」という声でなき、オスのような激しい声は出しません。
今回はキジについては音声を見つけられなかったので、コウライキジで紹介しています。
(50秒ごろ、2分30秒ごろ)
また、キジのオスは「ケン ケン」という鳴き声によってお互いの個体を識別しているんだとか。
スズメ目の仲間の複雑な音声ではなく、キジの比較的単純な音声にも複雑な情報が組み込まれているようです。
キジの美しさと日本人
キジ科の鳥類はときおり雑種をつくることが知られています。
驚くべき例は、キジとヤマドリのあいだで雑種が形成された記録があることです。
この場合、オスのキジがメスのヤマドリと交配し、雑種が形成されるとか。野外でも両種の雑種らしい個体が見られているようですが、非常に珍しいようです。
両種の中間的な姿をした個体を見つけたら、ぜひ写真をとって、専門機関に問い合わせてみると良いでしょう。
またキジは、大昔からその美しさで日本人の心に感銘を与えてきたことは疑いようがありません。
日本書紀が書かれた頃、本州でオーロラがみられた際には、オーロラを「キジの尾のようだ」と形容したとか(from nazology)。情報にあふれた現在ではなかなか思いつかない、粋な比喩ですね。
 トリハカセ
トリハカセキジをオーロラと表現するだなんて、昔の人は素敵だなぁ!



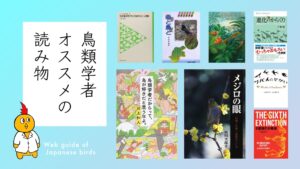


コメント