初夏の森ではキビタキやオオルリといった派手なヒタキが見られますが、コサメビタキは主役の1種です。
地味で写真映えしないなぁと見逃してしまう人は多いかもしませんが、その生態を知れば愛着が湧くこと間違いなしです。今回はそんなコサメビタキの生態や、近縁種との識別について紹介します。
 トリハカセ
トリハカセこの記事では可愛らしいコサメビタキに迫っていきます。
興味のある項目を目次から飛んでくださいね。
コサメビタキ入門編
コサメビタキ | Asian brown flycatcher | Muscicapa dauurica | スズメ目ヒタキ科サメビタキ属
レア度:★★★☆☆☆☆☆☆☆(3/10:適切な時期に自然がある場所で探すと見つかる)
見られる季節:夏
見られる場所:北海道から九州にかけた低地の森林
見られる環境:広葉樹林を好む
餌:昆虫やクモなどの節足動物や、時に果実
キバラガラは体長13cm、体重8–16グラムほどのスズメより少し小さい小型のヒタキ類です。
日本で普通に見られるサメビタキ属3種のなかでは、最も身近で観察することができる種で、山間部では繁殖の様子が観察できるはずです。
日本は繁殖時期のみ観察される夏鳥です。一見和風な見た目をしていますが(?)、意外にもその分布域は広く、アジア全域で見られる野鳥です。
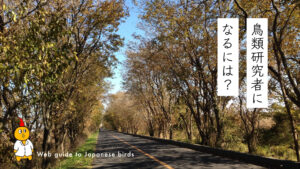
コサメビタキの生態
実は広大な分布域
コサメビタキの分布は実は非常にひろく、インドから日本に至るまでが分布域で、オーストラリアでも記録があります。
このうち、インドやタイ、中国中部から南部にかけては通年コサメビタキが見られます。それらの場所では「留鳥」なのです。
またマレーシアなど一部地域は越冬期のみ観察できます。とはいえ、熱帯雨林なので「冬」という季節ではありませんね。
日本はコサメビタキの分布域の東の端に位置します。渡り時には各個体が個別に渡ることが多いようです。
広葉樹林が大好き

コサメビタキが好む環境は、広葉樹林です。繁殖期・越冬期ともに広葉樹林で生活するのです。
カラマツ林などでも稀に見られますが、見つけるのなら低地の明るい広葉樹林が何よりおすすめです。
渡りの時期にはエゾビタキも低地の広葉樹林を通過しますが、基本的にサメビタキは低地の広葉樹林では少ないです。
生息地の雰囲気や季節も考えながら識別することで、種の識別の難易度は下がるはずです。
 トリハカセ
トリハカセ繁殖期は低地のコサメビタキ、亜高山のサメビタキと覚えましょう。
しっぽ自慢:繁殖生態
5−7月に基本的に一夫一妻で主に1度繁殖します。そして、夫婦で協力して縄張りを守る姿をよく見かけます。
4-5個の卵をメスが中心となって抱卵し、約2週間後の孵化からは夫婦で協力して子育てをします。
地味なコサメビタキですが、オスからメスへのアピールは情熱的で、可愛らしいです。
お腹をパンパンに膨らませ、尾羽を開き、左右に揺すります。実際の様子は、以下の動画をご覧ください。
ちなみに巣は、苔を器用に使って太い枝の上に作ります。
想像できない越冬期
夏のコサメビタキはイメージできますが、冬のコサメビタキの生活はどうでしょうか?
冬、コサメビタキはマレーシアなどの熱帯雨林で越冬を行います。
実際僕も、マレーシアを訪れた際に熱帯雨林で越冬するコサメビタキを観察したことがありますが、
生活の様子は、日本の夏とさほど変わらず、冬も樹上でフライキャッチで昆虫を食べるような生活を送っていました。
なお熱帯域にはコサメビタキなどの仲間が多数おりますので、識別の難易度は若干上がります。

サメビタキやエゾビタキとの識別点
コサメビタキ / サメビタキ / エゾビタキはお腹の模様で識別というのが一般的ですが、それだけでは結構難しいです。
はっきり言って、大阪南港野鳥公園のまとめ(リンク)が非常にわかりやすいです。
 トリハカセ
トリハカセ非常に正確で、イラスト、写真ともにまとまっていて
素晴らしい識別のまとめだと思います。ぜひチェックを!
このブログは形態や識別に特化した内容ではないため、識別点は大阪南港野鳥公園のまとめに譲ることとしましょう。
本ブログでは「こんな感じだよね」というイメージをお伝えしていきます(笑)

鳴き声
コサメビタキは、基本的にこちょこちょした小声でさえずります。
それもつがいが形成されるまで。夫婦になったあとは、こっそりと2羽の世界を楽しむようです。
また、さえずりの際には、他の鳥の鳴き声などを真似て、自分のメロディーにこっそり組み込んだりします。
低地の森林で、コサメビタキと似たようなさえずりの種はいないので、その特徴さえ覚えてしまえば識別は容易でしょう。

地鳴きは金属音のような、非常に高い鋭い声「ツィー」です。「チリリリ」と低めの声でないたりもします。
サメビタキの方がよりかすれていて、エゾビタキはもう少し柔らかい音の印象を受けます(個人的な感想です)。

夏の風物詩の今後はいかに?

 トリハカセ
トリハカセさすが広い分布域!
IUCNはコサメビタキの個体数の近年の傾向を「安定」と評価しています。
多くの渡り鳥が数を減らす現在、個体数が比較的安定している種というのは貴重かもしれません。
とは言え、渡り鳥は繁殖地である日本の環境だけでなく、越冬地を含めた様々な環境のうち、1つまたは複数の環境の健全さが失われてしまえば、個体数が大きく減少する可能性があるとも考えることができます。
身近でみられるコサメビタキの個体数を毎年しっかり記録し「いつの間にかいなくなっていた」とならないようにしなければなりません。
参考文献
・ピッキオ (2002) 鳥のおもしろ私生活. 夫婦と生活社, 東京.
・真木・大西 (2000) 日本の野鳥590. 平凡社, 東京.
・中村・中村 (1995) 原色日本野鳥生態図鑑 陸鳥編. 保育社, 大阪.
・清棲 (1978) 日本鳥類大図鑑 I & II. 講談社, 東京.
・The Cornell Lab of Ornithology (2023) Birds of the world.
・IUCN (2023) The IUCN red list of threatened species
・Clarke et al. (2009). Asian Brown Flycatchers Muscicapa dauurica on Ashmore Reef: First Records for Australia. Australian Field Ornithology, 26: 123-131.
・Mansor & Mohd (2012) Foraging patterns reveal niche separation in tropical insectivorous birds. Acta Ornithologica, 47: 27-36.



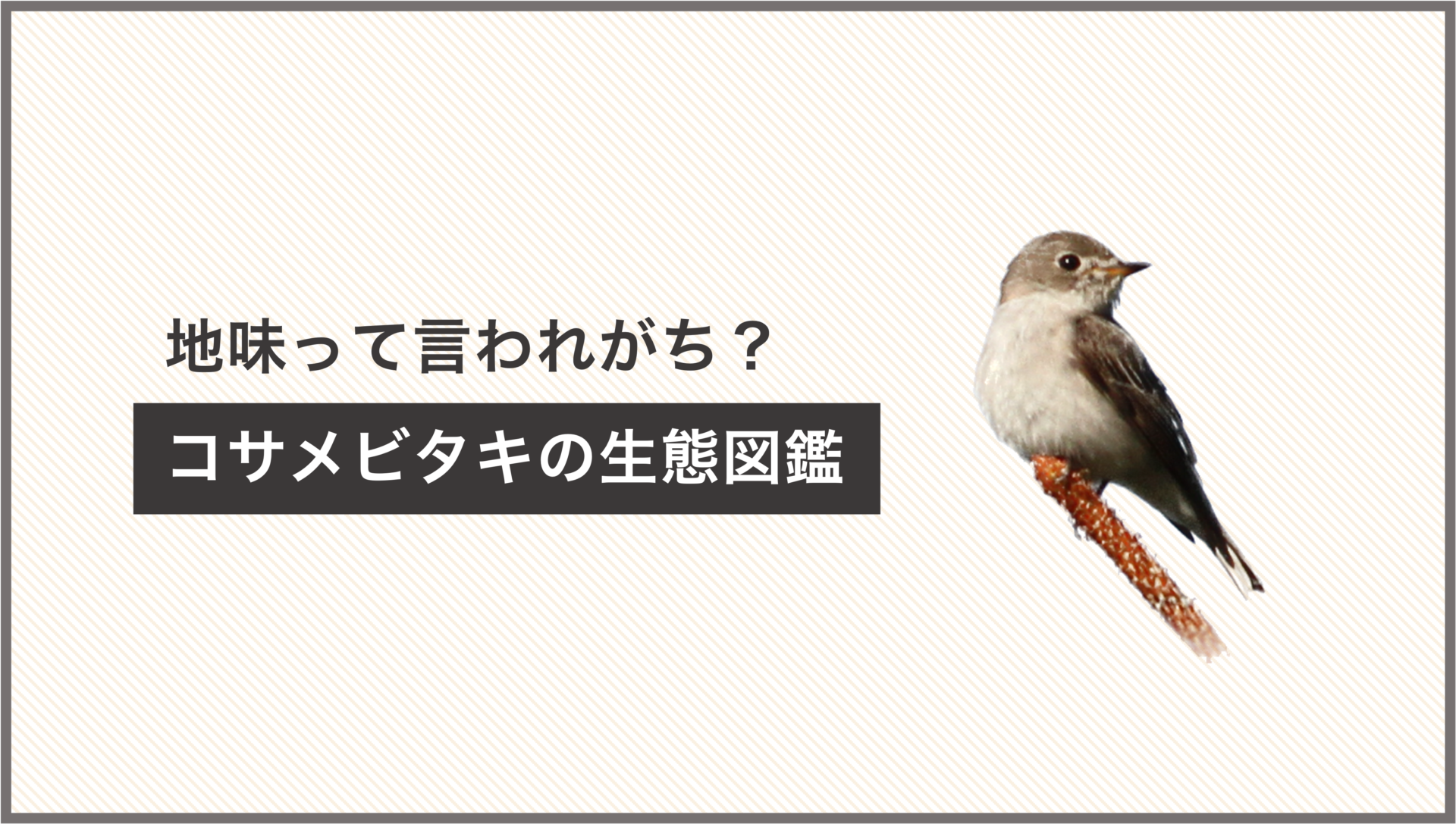
コメント