私たちは野外でのバードウォッチングという鳥との関わり方以外に、野鳥に「餌付け」といった関わり方をする場合もあるでしょう。
一般に餌付けは推奨されませんが、時に野鳥への愛ゆえの行動であったりします。
北米ではそんな愛から、庭に「ハチドリ用の人工的な花」を用意したりします。そんな人工花が、ハチドリの未来に強く影響していることがわかりました。
 トリハカセ
トリハカセ人間の影響は思わぬ形で、鳥に影響しているのです。

「ハチドリ用の人工的な花」といいましたが、これは蜜をハチドリに与える餌台(フィーダー)のことです。
庭のフィーダーにやってくるアンナハチドリ(Anna’s Hummingbird)は、北米の都市ではいわゆる普通種の1種です。2025年に発表された研究は、アンナハチドリの分布が過去160年のあいだ大きく北へと広がり、その分布拡大に庭のフィーダー(と外来種のユーカリ)が強く結びついていることを発見しました。
研究チームは、人が置いたフィーダーが、アンナハチドリの分布や個体数、形態にまで影響しているかも… そんな可能性を3つの材料から探りました。それは、① 昔の新聞の情報から「いつ頃から、どの町にフィーダーやユーカリが広まったか」を年表のようにたどり、② 冬のバードウォッチャー参加型の調査で「どこでどれだけ数が増えたか」を確認し、③ 博物館に残る標本を詳しく測って「くちばしの形がどう変わったか」を調べたのです。
分布と形の劇的な変化
研究の結果、アンナハチドリは分布を北へ、つまり高緯度域へと拡大していることがわかりました。
さらに、フィーダーが多い地域ほど、くちばしはストローのように細長く、真ん中が少しくびれた形へと近づいていました。上から見たくちばちの輪郭も、特にオスでよりシャープに。ユーカリの並木は個体数を後押しする追い風にはなったものの、くちばしの形そのものを変化させた原因はフィーダーだったという結論に至りました。
アンナハチドリは分布を北に拡大させたことで「フィーダー由来のシャープな形」以外の異なる特徴も表すようになりました。それは、北で生きる個体の嘴が短くなった、ということでした。
嘴はものを摘んだりする以外に、熱をにがす鳥にとって重要な機能があります。その機能が寒い高緯度地域ではアダになるのです。熱を逃さぬ短い嘴が生存上有利になった結果だと言えます。
都市でおこっている進化
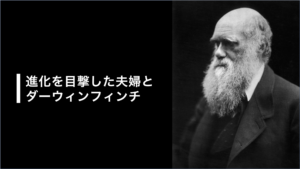
進化は気の遠くなる時間で起きるという常識のがこれまでの一般的な常識でした。しかし、ダーウィンフィンチの研究などから、そんな常識に意義が唱えられ始め、研究が蓄積してきています。
今回のアンナハチドリの研究例も、意義を唱える研究の1つです。人の暮らしが生む資源(フィーダー)がハチドリの生態を変え、世代を重ねるうちに形態へもその歴史が刻まれていくのです。しかも、たった100年程という短期間で、です。人間の住む都市部で、進化がまさに現在進行形で起こっているのです。
 トリハカセ
トリハカセ今後温暖化が進むと、さらに嘴の形が変化するのも?
私たちの孫の代には、いまいる身近な鳥の姿も変わっているかもしれません。
 トリハカセ
トリハカセ写真を撮るための、身勝手な餌付けなどはやめましょうね。
参考文献
・Alexandre et al. (2025) Supplemental Feeding as a Driver of Population Expansion and Morphological Change in Anna’s Hummingbirds. Global Change Biology, 31:e70237.


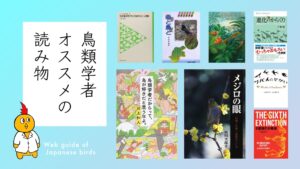
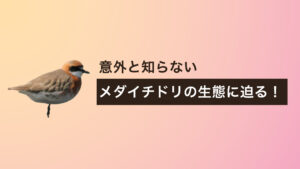
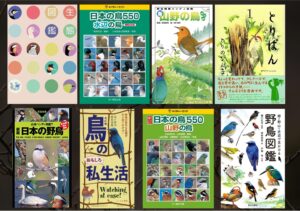


コメント